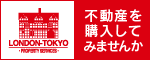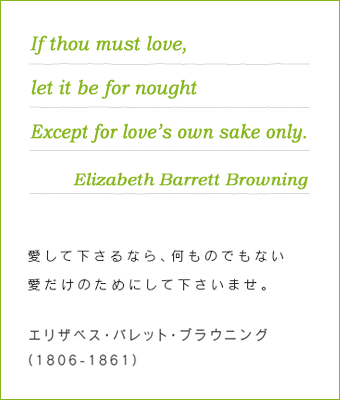
19世紀英国を代表する女流詩人で、やはり詩人だったロバート・ブラウニングの妻であったエリザベスの愛の詩の一節。後に桂冠詩人となった夫の方が今では有名だが、エリザベスの生前には、圧倒的に彼女の名声の方が上だった。
引用した句の後には、その微笑や容貌、やさしげな話しぶりのために愛しているなどとは言わないで、と続く。真に人間性への共感に立脚した純粋な愛によって自分を愛してくれと、そう主張しているのである。「nought」は「naught」とも書き、「nothing」の古い言い方であるが、「nought except(それ以外の何ものでもなく)」という限定の強調形が、愛の真実を求め、訴えるエリザベスの気迫をよく表している。
至純の愛、そして永遠の愛を彼女は望んだ。男女が互に、その存在の核に当たる部分に触れ、がっちりと組み合う、そのような愛。人格を尊び、敬い合う高邁な愛。可愛いねとか、きれいだなどと誉めそやす次元に留まる愛は、永続しない。どれほど魅力的であろうと、容貌など時の経過によって否応なく変わるものなのだから……。
また詩の後半ではこうも言っている。憐れみのゆえに愛さないで。憐憫の情の心地よさではダメなのだ。慰みを長くもらえば、涙も出なくなる。その時、愛は消滅する。
エリザベスは15歳の時に脊椎を痛め、以後も病弱だった。詩人としての名声はあっても、自宅に籠もりきりの暮らしだった。ロバートと出会ったのは39歳の時だが、もともとはエリザベスの詩を読んで感動したロバートが手紙を出し、文通からやがて家への出入りを許されるようになり、愛に発展したのだった。憐れみでは嫌、という彼女の真意は、病弱の身を措いては考えられない。
それにしても、愛というものに真剣な時代だった。愛に打算や妥協はありえず、魂そのものでなければならなかった。近頃流行の、限りなく遊戯に近いライトな恋愛など、彼らの辞書にははなから載っていなかった。その突き詰め方の一途さを、つき従うことが難しく感じる向きもあるだろうが、愛の光芒が放つ鮮烈さは、時空を超えて輝いている。
父に結婚を反対されたエリザベスは、ロンドンのマリルボーン教会でロバートと秘かに結婚、1週間後にはイタリアに駆け落ちする。そして夫妻は、エリザベスが現地に客死するまで、仲睦まじくイタリアに暮らした。
至上の愛を欲した人は、愛を人生における至上のものと考え、疑いを持たなかった。信念としての愛に生き、その愛に殉じた。愛に一途に生きた人の言葉は、今もって美しい。
| < 前 | 次 > |
|---|



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?