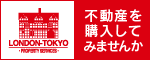第2回 ビッグ・イシューいかがですか。
ロンドンの街中を歩いていると、時々、「ビッグ・イシュー、ビッグ・イシュー」という声が聞こえてくる。ほとんどは、地下鉄駅の出入り口や繁華街の一角だ。振り向くと、たいがいは、粗末な衣服をまとった男性である。そして、不器用そうな声で「ビッグ・イシュー、1冊、いかがですか」と呼びかけてくる。
ロンドンに少し住んでいれば、必ず、目にする光景だ。
「ビッグ・イシュー」はホームレス支援の週刊誌で、発行元がホームレスの人々に販売を委託する。1991年の創刊後、世界中に広がり、2003年からは大阪や東京などで日本版の販売も始まっている。英国では1冊1.5ポンド、このうち80ペンスがホームレスの収入になる。
創刊者のジョン・バード氏(61)は以前、北海道新聞の取材に答え、こんなことを話していた。
「ニューヨークの街路でホームレスが雑誌を売っているのを見た友人から、創刊を勧められてね。『君は元ホームレスだったから適任だよ』って。私は家庭が貧しく、盗みなどを繰り返して少年院に入り、20代まで何度もホームレスになった。その経験から、ホームレスを脱するには働いて、自活することが最も大切だと痛感してたんだ」
だから、バード氏は、ビジネスとしてホームレスを支援しようと、雑誌を創刊した。ホームレスは、政府などから支援を受けることが当然だと思われていた時代。そんな中、彼はホームレスにこう言い続けた。
「これはビジネスなんだ。だから物ごいするな」」
話は、30年近く前に飛ぶ。
20代の私は、初めて海外への旅に出かけ、最初の訪問地、バングラデシュを訪れていた。
ダッカ空港到着は深夜だった。空港から市内行きのバスに乗ると、ほとんどの窓にガラスがない。バス内部の後ろ半分には牛が乗り、乗客は狭い座席に押し込まれた。
ほどなく、出発前のバスは大勢の子供やホームレスに取り囲まれた。外から窓枠にしがみついた人々が、いっせいに「お恵みを」と言いながら、窓から座席の方へ手を伸ばす。その数はどんどん増えた。
「ご主人さま、お恵みを」
「お恵みを」
「ご主人さま!」
バスが動き始めても、多くの人は窓枠にしがみついたままだ。スモールの前照灯しか点けないバスは、暗い道路を疾走する。室内にも灯りはない。その中で、無数の手が、なおもコインを求めて座席の間をさまよっていた。私の席の外側では、子供が振り落とされまいと窓枠にしがみつき、私の顔を見続ける。ダッカの市街地に差し掛かって、バスがいったん停止したとき、ようやく彼らはあきらめ、バスから飛び降りた。
このとき、私は「絶対に『施し』はしない」と決めていた。「施し」はしょせん、「持てる者」から「持たざる者」への、「お情け」にすぎないと考えていたからだ。
「貧困の解決には、先進国や多国籍企業が、途上国経済を支配する構造そのものを変える必要がある。それを放置したままで、チャリティーに走るのは、欺瞞(ぎまん)と偽善でしかなく、改革を遅らせるだけだ」と。
あれから、多くの時が流れた。
世界の「構造」は今も変わっていない。日本や英国は依然として「持てる国」であり、それぞれの国の内部にも「持てる者」と「持たざる者」は厳然と存在する。そして、「構造」はさらに強固になってきた。
変わったのは、自分である。ロンドンの街頭で「ビッグ・イシュー」を買うようになった。彼らを見かけると、なかなか素通りができない。同じ号を買ったこともある。
「単なる自己満足だ」と言われれば、その通りだと思う。それでも、私は買う。家族も買う。何しろ、ロンドンの冬は寒いのだ。冬でなくても、都会は寒い。彼らの人生は知る由もないが、好きでホームレスを続ける人はいないと思う。
今年の「初買い」は、正月明けの4日だった。ピカデリーの劇場近くの繁華街。雨の夜、道ばたに座り込んだ彼は、声も出さず、濡れたビッグ・イシューを手にしていた。少し多めの硬貨を目にして、彼は口元を動かした。雑踏の中でよく聞き取れなかったが、こう言ったと思う。
「ありがとう ─ God bless you」



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?