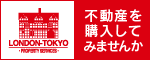第9回 極右が躍進した街。
ロンドン東部に「Barking and Dagenham」という地域がある。日本人はあまり住んでいないし、観光名所があるわけでもない。
ロンドン中心部から地下鉄で小一時間。線路が地上に出て、少し進むと、古い建物が多いロンドンには珍しく、鉄筋コンクリート造りの高層住宅が林立する景色が見える。そこがBarking and Dagenhamだ。
この地域は、2年前の統一地方選の際、極右政党の「英国国民党」が大躍進したことで知られている。国民党の議席はゼロだったのに、そのときの区議会議員選挙では、13人の候補者のうち12人が当選。いきなり、議会の第二党になった。文字通りの大躍進である。
「極右」と聞くと、どうしても、ナチス・ドイツとか、真っ黒な「街宣車」から大声で何かをがなり立てる日本の右翼を想像する。でも、Barking and Dagenhamで新たに議員になったロバート・ベイリーさん(41)は、実に、人当たりがいい。
「英国の文化が移民によって破壊されている。そこに危機感を抱き、国民党に参加しました」
そんな風にベイリーさんは話し始めた。穏やかな、どちらかと言えば、ぼそぼそした語り口。事務所の壁に掲げた、白地に赤のイングランド旗が、かろうじて「極右政党」を思い起こさせてくれる。
「例えば住宅です。ここの窓からも高層住宅がたくさん見えるでしょう?移民のために安い住宅を、とつくられたんです。しかし、英国の文化じゃありません。小さくても家は戸建て。庭があって、壁はレンガを積んで、暖炉もあって。それが英国文化。住宅だけじゃない。いろんな文化や習慣、伝統、生活が、移民の大量流入で破壊されているんです」
国民党は選挙の際、「反イスラムの国民投票を」「子供たちのために英国の伝統を守ろう」などと訴えていた。もっとも、そんな標語だけで大躍進したわけではない。
Barking and Dagenhamの人口は約16万人。ベイリーさんのような英系白人は8割を占め、圧倒的な多数派だ。それなのに「移民への恐怖感は住民全員が持っている」という。
「彼らは英語もまともに勉強しないでしょう?固まって住み、僕らとの交流もほとんどない。隣人が何を話しているのか、何を考えているのか、分からない。だから、僕だって怖い。地域を捨て、ほかへ移り住む白人も増える一方なんですよ」
ベイリーさんの事務所から、そう遠くない繁華街の一角に、小さなギリシャ料理の店がある。
移民団体の代表を務める50歳間近の男性と、その店内の壁側の席で会った。匿名にするほどの取材内容でもないと思うのだが、彼は「匿名にしてくれ」という。とくに、英国民党に対する考えを聞いた後は、余計に神経質になった。声はさらに小さくなり、ひそひそ話同然だ。
「白人対移民だけじゃなく、移民対移民でも同じだけど、みんな、キレやすくなった。ささいなことで、すぐ怒る。いらいらが募っている。でね、キレた人のはけ口になるのが、俺たちなんだ」
この地区では6年前、地域で最大規模だったフォードの自動車工場が完成車ラインを廃止し、数千人が失職した。区役所の統計によれば、今では16歳以上の4割は定職がない。そして「事件」が増えてきたと言う。
「イスラム女性のベールを街頭でいきなり、はぎ取る。車に傷を付ける。つばを吐きかける。石を投げつける。こういうことの痛みは、やられた方しか分からないんだよ」
移民問題は根が深い。時間が経過すれば、融合が進むかと言えば、そうでもない。実際、この地区に長く住むパキスタンからの移民一世、ラジャ・スナウラ・カーンさん(45)は、こんなことを語った。
「自分たちもいろんなことがあったが、子供たちの世代はいつの間にか、仲間内だけで通用する言葉や文化を持ってしまった。他民族と交わりながら英国で生きる努力をせず、不遇な目に遭うと『人種差別だ』と騒ぐ。何かあると、すぐ『移民のせいだ』と言う英国の人々と同じだよ」
おそらくはカーンさんも、つばを吐きかけられたり、石を投げ付けられたり、という経験を数多く持っているに違いない。そうした悔しさと、英国に根付いたという自負。それらが絡み合った、複雑な言葉だった。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?