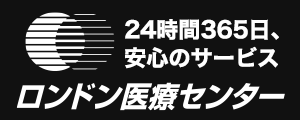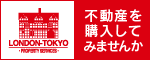第16回 罪は罪じゃと思うてました。
少し前、ルクセンブルク国会が安楽死法案を可決したというニュースがあった。この夏にも正式に成立する見込みだという。ベネルクス3国では、オランダが2002年、世界で初めて安楽死を合法化し、ベルギーも安楽死を認めている。
英国は、世界で最初に安楽死(尊厳死)の合法化を目指す団体「安楽死協会」ができた国だ。1935年のことである。現在も合法化には至っていないが、協会設立の翌年には早くも安楽死法案が議会に上程され、審議されている。
そんな流れを資料で追っているうち、10数年前に西日本地方で取材した男性のことを思い出した。
7月末の暑い日。
私はある中堅都市の弁護士事務所を訪ねた。書類の山、書き込みだらけのホワイトボード、くたびれた茶色のソファ。弁護士は「クーラーは体に悪いから」と言って窓を開け、扇風機だけを回している。
その暑さの中、横の別室から「彼」は現れた。白いシャツに白いズボン。60歳が目前だったが、実年齢よりはるかに老けて見えた。
「事件」が起きたのは、1990年代初めの、ある春の夜である。この日は冷え込みがきつく、温暖なこの街も夜は気温が7度まで下がった。
夜9時ごろだったという。彼は自宅の風呂に湯を張った。末期がんで一歩も動けぬ妻を背負って、風呂場に行き、体を洗ってあげた。
やがて妻が言った。
「ここで」
傍らにはカミソリがある。「ここで死にたい。ここで切るき(から)」。そして、自殺できるまで出て行って、と。その言葉で彼は居間に戻った。
妻の発病は1985年である。
3つの病院で入院治療したものの、病状は悪化し、医師は事実上の「不治」を宣言。見放された妻は「もう家に戻りたい」と懇願し、自宅療養を始めた。彼は看病のため会社を休職し、やがて退職する。子供はいない。彼は妻の口に食事を運び、痛いと言われれば体をもんだ。
それでも痛みは激しさを増し、妻はやがて「死にたい」と漏らし始める。そして排ガス心中を何度か試みた。この日も死に場所を求めて川べりを車で走り、夕方に戻ったばかりだった。
日付が変わった午前2時。
風呂場に行くと、妻が彼を見て訴えた。細い、細い、声だった。
「死にこくったき(損なったので)、手伝うて」
その後の行動を彼はよく覚えていない。結婚から27年。彼の両手で最期を迎えた妻は、その瞬間、何の言葉も発せず、じっと彼を見据えていたという。
事務所では、扇風機が低い音を立てながら回り続けていた。
弁護士は「患者は自己決定権がある。彼の妻は安楽死を強く希望していました」と語った。「あの状況では、彼は他の手段を取り得なかった。そして最愛の妻の希望を最後の手段でかなえた。その夫に法律上の非難を加えることができるでしょうか」
裁判所はその主張を認めない代わりに、「温情判決」で応えた。嘱託殺人罪で懲役3年、執行猶予1年。猶予期間は刑期を下回っている。
この事件は西日本地方の新聞で小さく報道されただけだが、これと同種の事件は少なくない。しかも、そうした事件の犯人や被害者の肉親は、たいてい、高齢者であったり、医療や介護を十分に受ける経済的余裕がなかったり、である。自分たちへの支えが何もない中で迫られる決定。それを、真に自己決定と呼べるのだろうか。
彼は取材中、私を見詰めているようで見ていなかった記憶がある。
「事件は片時もよう忘れません……悪いことをしたとも、ええことをしたとも思いません。とにかく、毎日、痛い痛いと言う女房がかわいそうで、かわいそうで、早う、死なせちゃりたいと。それだけでした」
「あれで良かったんじゃろか、間違ったんじゃろか……それは今も分かりません。罪は罪じゃと思うてました。刑務所に行くつもりでした。執行猶予で良かったかどうか、それも分かりません。本当に何も、自分では何も分からんのです」
彼はその後も妻と暮らした自宅に住み続けていた。元気なら今も、きっと、そこに居る。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?