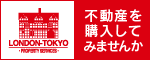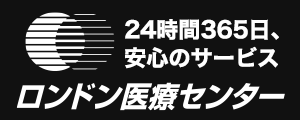第39回 人々のスポークスマンとして。
スタッズ・ターケルがシカゴの自宅で死去したのは11月1日だった。96歳だったという。作家であり、ラジオの脚本家・パーソナリティーでもあった。何よりも彼を有名にしたのは、市井の人々の膨大なインタビューを集めた「良い戦争」「アメリカの分裂」などの著作である。
私は学生時代からターケルのファンで、とくに「仕事!」を愛読していた。邦訳は2段組で700ページ超もあり、115職種の133人が登場する。逝去を伝えるBBCがターケルを「Studs Terkel was the spokesman for millions of Americans」と表現したのも道理だ。名も無き人々の前にテープレコーダーを置き、ひたすら話を聞き、言葉を引き出す。それがターケルだ。
ターケルの仕事とは比べるべくもないが、10年ほど前、私が言い出しっぺになって、同僚と一緒に市井の人々のインタビューを北海道新聞に長期連載したことがある。要は「仕事!」のまねである。方言は方言のままで、口癖は口癖のままで。人の話しぶりは、まさに、生き様を反映しているからだ。
離島航路のパイロット、温泉旅館の仲居、セールスマン、コンブ漁師、消防士、稲作農家……。私たちが手掛けた「しごといきる」にも100人以上が登場する。例えば、定年退職したばかりの路線バスの運転手。彼は約20年間、人口10数万人の都市で路線バスの運転手を続けた。その前は長距離トラックの運転手。ハンドルこそが人生だった。
「……事故を起こしたら、ってことが頭から離れなかった。私なんか2カ月に1回は夢を見てたね。バスに満員の乗客を乗せて、あああ、ブレーキが利かない、あああ、ぶつかるぶつかる。その瞬間に目が覚める。そういう夢です。運転手なら同じような夢、みんな見てますから。間違いなく見てるから。トラック時代は、とにかく眠くてね。日中は小樽近辺で荷物を運び、夜8時から帯広行きの運転席に座る。着くのは翌朝でしょ。して、すぐ帰り荷を積んで小樽へ戻る。残業は毎月、150時間から200時間。今と違って労働基準法とか関係ない世界さね。体が丈夫だったから持ったけど、すごい睡魔なんだわ。運転中は左手でハンドル持って、右手は髪の毛ひっつかんだり、足をつねったりで。あああ、と気が付いたら、反対側車線走ってた。そういうことが2回あった。運がいかったんだ。紙一重だよ。あの時、対向車が来てたら、いまのおれはないもの。人生変わってたよ」
「辞めたくなったこと? あるあるある。トラックの時もバスの時も。人間関係だ何だって、いろいろあるっしょ。バス会社を辞める時も嫌な思いをした。でもね、今は何とも思わない。恨みとか嫌な思いだけを抱えて生きていけない。明るく楽しく、さ。二女が生まれた時もね、大変だとか思わなかった。7歳で亡くなったけど、あの子は生まれつき脳に障害があって、親の顔もわかんない、言葉も言えない。そういう子だったの。でも、とにかく、めんこい子でね。周囲は、大変でしょう、と言うけど、何が大変なものか。普通の子供とおんなじですよ、私らにしたら。あの子が生まれたのは、ちょうどバスが嫌で嫌でしょうがなかった時期だけど、おれが踏ん張らなきゃ、って。親は子供のために頑張れるんだから。子供はかわいいに決まってるっしょ。嘆き悲しみなんて、ほんの一時のものでしょ?」
彼には夢があった。定年の日は自分で回数券を買い込み、乗客に手渡しながら、「きょうで私のハンドル人生は終わります、ありがとうございました」とアナウンスするのだ。しかし、定年の数日前、彼は車庫で倒れた。脳出血だった。彼は、そのときの悔しさを一生忘れない。
ターケルの「仕事!」に登場するレンガ積み職人は「自分が積んだレンガの塀は、今でもすべて思い出せる。若い時の仕事の前を通ると、全部崩してやり直したくなるんだ」と言う。この運転手も、過去に乗ったトラックとバスのナンバーを全部そらんじていた。
日々の仕事は単調で退屈で、もちろんニュースにもならない。でも、私はそこにひかれる。ふつうの人々が織り成す、ふつうの日々。時に見失いがちな「希望」も含め、社会と時代のすべてはそこにある。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?