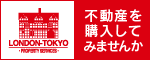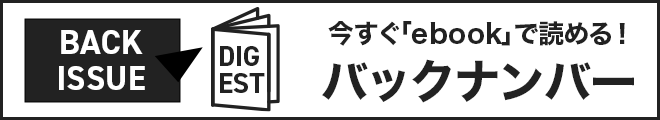緑を分かち合う社会へロンドンの進化する庭
公園が多いといわれながらも、家の周辺や街路樹などの身近な居住空間、つまり日常的に利用できる緑地は減少傾向にあるというロンドン。そんなロンドンで近年、自然を育てることを目的にした、開かれた新しい形の庭が静かに育ちつつある。この特集では、人と自然の関係を問い直すような、庭の再定義に取り組む人々や場所を取り上げ、その共有と変化の可能性を見つめてみたい。
(文: 英国ニュースダイジェスト編集部)
参考: www.nhm.ac.uk、www.culpeper.org.uk、https://ideasforgood.jp、https://omvedgardens.com、BBC、The Guardian ほか
 聖ポール大聖堂の隣にある屋上公共庭園、リフレクション・ガーデン
聖ポール大聖堂の隣にある屋上公共庭園、リフレクション・ガーデン
市民の庭を再定義
庭を「自然を共有し育てていく場所」と定義し、それが地域の人や地球を癒やすことにつながると考えられている例を紹介する。
コミュニティー・ガーデン
公園が行政によって管理、運営されるのに対し、コミュニティー・ガーデンは、場所の選定から運営まで、地域住民が責任をもち自主的に担うことが特徴だ。始まりは1970年代の米国で、英国でも80年代から環境保護運動の高まりとともに整備が進んだ。欧州には古くから都市部で農地をリースし共有するアロットメント(市民農園)が存在しており、コミュニティー・ガーデンとの類似点もある。その違いとしては、アロットメントが個人や世帯が野菜の自家栽培目的で仕切られた区画を借りて使うのに対し、コミュニティー・ガーデンは野菜だけでなく花の栽培や憩いのスペースも含み、地域のつながりや教育、福祉、環境意識の向上などが目的の場所である。
ロンドン北部にあるカルペパー・コミュニティー・ガーデンは、誰にでも開かれた庭として、住宅地の真ん中に位置する。80年代に作られたこの場所は、都市化によって奪われた自然や居場所を、市民の手で取り戻す試みとして始まった。今では近隣住民やボランティア、身体や精神の健康を回復させる園芸療法のために通う人々など、さまざまな背景を持つ人々が植物を育て、空間を共有している。こうしたコミュニティー・ガーデンは、孤立、気候変動、メンタル・ヘルスの問題など、現在の都市が直面している課題に対する小さな答えの一つともいえる。

未来を創る実験場に
一方、庭そのものがフィールド調査の場として活用される試みも始まっている。例えば、ロンドン自然史博物館が2024年に再整備した中庭を使った「アーバン・ネイチャー・プロジェクト」(Urban Nature Project)では、野生動物の生息環境としての庭の価値を再発見しようとしている。このプロジェクトでは、都市における生物の多様性を市民とともに調査、記録し、教育資源としても活用されている。庭は未来を創るための実験場でもある。その姿を記録し、公開し、次の世代へと継承することは、人と自然の関係性を問い直す持続的な活動となりつつある。
また、次世代に向けた自然教育の動きも活発化している。政府は25年9月から、中等教育修了資格の一つであるGCSEの新科目として自然史(Natural History)を導入する予定だ。これは、自然環境や気候危機、持続可能な生活についてを理論だけではなく実践で学ぶ新たな科目であり、教室の外、つまり庭や森といった実際の自然環境を学びの場として捉え直すものだ。10年以上にわたりこの導入を求めてきた博物学者メアリー・コルウェル氏は、「地元の自然に触れ、観察する力こそが、未来を考える基盤になる」と語る。庭は今、教育の最前線になろうとしている。
社会を耕す庭師たち
都市の緑を守り育ててきた、ファニー・ウィルキンソンとゲリラ・ガーデナーという、時代も立場も異なる庭師たちの活動に光を当てる。
英国初の女性庭師ファニー・ウィルキンソン
ファニー・ウィルキンソン(Fanny Wilkinson 1855~1951年)は、英国で初めてのプロフェッショナルな女性ランドスケープ・ガーデナーであり、ヴィクトリア朝時代のロンドンにおける都市緑化と女性の社会進出に大きく貢献した先駆者的存在だ。ウィルキンソンの活躍した19世紀後半のロンドンは、産業革命の影響で人口が爆発的に増加し住宅や工場が密集する一方で、緑地は次々と失われていた。特に労働者階級が暮らすロンドンの東部や南部では、公園や広場などの公共スペースがほとんど存在せず、人々は過密で不衛生な環境に置かれていた。
 女性庭師の草分けファニー・ウィルキンソン
女性庭師の草分けファニー・ウィルキンソン
このような背景のなか、ウィルキンソンはメトロポリタン公共庭園協会(MPGA)と共に、教会の墓地跡や空き地などを活用し、誰もが自由に使える緑地として公共庭園を都市の中に設けていった。それは単なる美観のためではなく、労働者の健康と精神のケアのための場所として機能することが重視されていた。ウィルキンソンは20年以上にわたり、労働者階級地域を中心に75以上の公共庭園を設計し整備。代表作には、ロンドン南部カンバーウェルのマイアッツ・フィールズ・パークや東部ベスナル・グリーンのミース・ガーデンズなどがある。
マンチェスターの裕福な家庭に生まれたウィルキンソンは、1882年にクリスタル・パレス園芸学校に、女性として初めて入学。ロンドン暮らしを始めたウィルキンソンの隣人は奇しくも著名な婦人参政権運動家ミリセント・ギャレット・フォーセットだった。園芸学校を卒業後、メトロポリタン公共庭園協会のランドスケープ・ガーデナーとして働き始め、86年には正式に報酬を得るプロフェッショナルな庭師としての地位を確立。87年までにはカイル協会(Kyrle Society)の造園家にもなっていた。カイル協会は、ナショナル・トラストを設立したオクタヴィア・ヒルの妹、ミランダ・ヒルにより作られ、過密な貧困地域に空間を確保し、公共庭園として整備することを目的としていた。そのような空間の一つが南部ヴォクソール・パークで、ウィルキンソンは開発業者から庭園を守るキャンペーンを成功させた。
また、ウィルキンソンは女性の権利向上にも尽力した。フォーセットの影響から女性参政権運動に関与し、スワンリー園芸大学の初代女性校長として女性の園芸教育を推進。さらに、第一次世界大戦中には女性農業・園芸国際連盟(Women’s Agricultural and Horticultural Union)の設立に関わり、女性農業労働者の育成に貢献した。ウィルキンソンの功績は長らく忘れられていたが、2022年にはロンドンのシャフツベリー・アベニューの旧居にイングリッシュ・ヘリテージによるブルー・プラークが設置され、25年7月には南部ワンズワースのコロネーション・ガーデンズに銅像が設置される予定になっている。
 2022年にやっとブルー・プラークが設置された
2022年にやっとブルー・プラークが設置された
ゲリラ・ガーデナーたちの静かな抵抗
英国のゲリラ・ガーデナーは、公共空間や放置された土地に無許可で植物を植えることで都市環境に緑を取り戻そうとする活動家たちを指す。特定の団体ではなく、理念を共有する個人やグループによる緩やかなネットワークで構成されているのが特徴だ。このムーブメントが注目を集めるようになったのは2000年代初頭で、とりわけロンドン南部在住のリチャード・レイノルズ(Richard Reynolds)が04年に始めた活動が広く知られている。レイノルズはロンドン南部エレファント&キャッスルの放置花壇に、夜中にこっそり花を植えたことから、「モダン・ゲリラ・ガーデニング」として注目を浴びた。その後、ブログや書籍を通じて活動を広め、ゲリラ・ガーデニングは国際的にも知られるようになった。
 2000年にロンドンのパーラメント・スクエアで起きた、
2000年にロンドンのパーラメント・スクエアで起きた、
反グローバリゼーション・デモ時のゲリラ・ガーデニング
現在では、地方議会の対策を待たずに自ら行動を起こす第二世代のゲリラ・ガーデナーたちが登場している。ここ数年の緊縮財政の影響で地方自治体は公共スペースの維持が難しくなり、しばしばそれらを民間に売却している。英国のシンクタンク「ニュー・エコノミクス・ファンデーション」の報告によれば、近年開発された住宅地域では、19世紀後半から20世紀初頭に建てられた住宅が多い地域と比べて、緑地の割合が最大40パーセントも少ないという。これは、まさにヴィクトリア朝時代の過密なロンドンで起きていた事態の再来ともいえる。現代においては、庭師ファニー・ウィルキンソンの役を務めているのは市民で、一般市民が街路樹の根元に球根を植えたり、路肩に在来種の野花をまいたり、空き地を区画してコミュニティー・ガーデンを作ったりと、小さなゲリラ戦士として行動している。
目立つ活動としては、ロンドン西部チズウィックで2010年に設立されたボランティア団体「アバンダンス・ロンドン」が、都市環境における自然保護と人々の自然とのつながりを取り戻す活動を行っている。主に植栽を中心とするが、カウンシルに許可を得ての活動と、時にゲリラ・ガーデニングによって、地域に新たな緑化空間を生み出そうと奮闘中だ。
庭にまつわるイベント3選
ロンドンで開催のさわやかな初夏の時期にふさわしいイベントを紹介。
1歴史から学ぶガーデニング Unearthed: The Power of Gardening
 中世薬草学の写本「Old English Herbal」
中世薬草学の写本「Old English Herbal」
大英図書館では、ガーデニングという行為がいかに人々に癒やしを与え健康を促し、地域のつながりを深めたり、見捨てられた空間を再生し、社会に変化をもたらすかを明らかにするエキシビションを開催中。園芸がどのように進化してきたのか、植物が大英帝国時代の植民地や自治領などから運ばれた経緯を探るほか、ガーデニングが気候変動による自然界への影響をいかに和らげることができるかという未来の可能性にも目を向ける。
また本展では、園芸がいかに社会的、政治的運動と関わってきたかにも焦点を当てる。例えば、イングランド内戦期(1642~51年)に囲い込み政策に抗議したディガーズ(Diggers)やトゥルー・レベラーズ(True Levellers)と呼ばれた農民たちの活動、20世紀初頭の都市計画運動であるガーデン・シティ運動、そして現代においては、種入りの爆弾(Seedbom)を使って放置された都市空間に花を植えるゲリラ・ガーデナーたちなどが紹介されている。ハイライトは、英国初の園芸マニュアル、ビーグル号の航海で植物標本を収集するために使用されたチャールズ・ダーウィンの導管、そして唯一現存するイラスト入りの「Old English Herbal」という中世薬草学の写本だ。
Unearthed: The Power of Gardening
2025年8月10日(日)まで
月、水~金 9:30-18:00 火 9:30-20:00
土 9:30-17:00 日 11:00-17:00
£15
British Library
96 Euston Road, London NW1 2DB
Tel: 01937 546 654
King's Cross St. Pancras / Euston
https://events.bl.uk
2秘密の花園に潜入できる London Open Gardens
 テート・モダンの敷地内にあるコミュニティー・ガーデン
テート・モダンの敷地内にあるコミュニティー・ガーデン
歴史的な建造物や優れたデザイン建築の内部が一般に公開される、毎年恒例のイベントに「オープン・ハウス・ロンドン」があるが、こちらはそのガーデン版。普段は非公開のロンドンの隠れた庭や緑地100カ所以上が一般公開される、2日間の特別なイベントだ。主催はチャリティー団体のロンドン・パークス&ガーデンズ(London Parks and Gardens)で、訪問者は歴史ある中庭や屋上庭園、コミュニティー・ガーデン、アロットメントなど、多様な緑地を巡ることができる。また、ガイド付きツアーやサイクリング・ツアーなども用意されているほか、庭園の管理者や専門家から直接話を聞く機会もある。首相官邸であるダウニング街10番地の裏庭など、特別な場所へのアクセスは残念ながら早期締め切りの抽選制だが、ほかにも魅力的な庭が多数公開される。
なお、このイベントの収益は、ロンドンの都市緑地の保護と維持活動に充てられる。庭を通じて、都市の歴史や文化、そして人々の生活とのつながりを再発見する貴重な機会となるはずだ。公式サイトでは、今年公開される庭園の基本情報が確認できるほか、あらかじめ予約しないと入場できない庭なども、同サイトから予約できる。
London Open Gardens 2025
2025年6月7日(土)、8日(日)
£24(2日券のみ。事前予約ガイド・ツアーは別料金。
12~17歳は£10、11歳以下は無料)
https://londongardenstrust.org
3緑や庭の大切さを学ぶための新しい施設 OmVed Gardens
 さまざまなイベントが開催予定のOmVed Gardens
さまざまなイベントが開催予定のOmVed Gardens
ロンドン北部ハイゲートにあるOmVed Gardensは、5月31日、英国初の「食・エコロジー・創造性のためのセンター」を標榜した教育施設をオープンする。もともと地域住民のためのガーデン・センターだった土地が、大人も子どもも楽しみながら自然との共存を学べる場所に生まれ変わった。開館に先駆けて発表された2025年の年間プログラムは、「しなやかな回復力を育む」(Growing Resilience)をテーマに、先に述べたロンドン・オープン・ガーデンズや、都市に緑を増やすことの大切さを提唱するグロウ・アーバン・フェスティバル(6月7~15日)などと連携しながら、さまざまなイベントを展開していく予定だ。
このセンターでは、種まきから発芽、成長、収穫、そして食卓に上るまでの食用植物のライフサイクルを学べ、訪れる人々が五感を通して自然とつながる場となる。文字通り、そして比喩的にも「種をまく」ことを重視し、健やかな未来のために今できる小さな行動を育てていくことを目指す。プログラムは大きく三つの軸に分かれている。
「庭から学ぶ」ことをテーマにした体験型プログラムが並ぶ、ワイルド・ラーニング(Wild Learning)では、ガイド付きの庭園ツアー、生態観察、コンポストや種の保存、植物種の識別など、身近な自然の中にある複雑で繊細なつながりを探る。7月20日には、エコロジストのキラン・リー氏による「バタフライ・バイオブリッツ」が開催され、野生生物調査の機会を提供する。
ヘルシー・ハビッツ(Healthy Habits)では、「再生する庭」と題した全5回のワークショップ(6~11月)を通して、自然との関わりや持続可能な栽培法を学ぶ。また、8月30日には「家庭のハーバリズム」として、野草やハーブを安全に採取、栽培し、チンキやお茶などを作る方法を学ぶ実践講座も予定されている。
最後は、自然をインスピレーション源とした創作活動や対話の機会が設ける、ネイチャー・レッド・クリエイティビティー(Natureled Creativity)。「納屋の対話」(Barn Conversation)と題されたセッションでは、各回にアーティストのヴィヴィアン・シャディンスキー氏や研究者のヘレン・バーナード氏、造園家ポール・ガザーウィッツ氏らが登壇し、「自然とともに設計する」などのテーマで語り合う。
OmVed Gardens
2025年5月31日(土)~ 詳細はウェブサイトを参照
1 Townsend Yard, London N6 5JF
https://omvedgardens.com

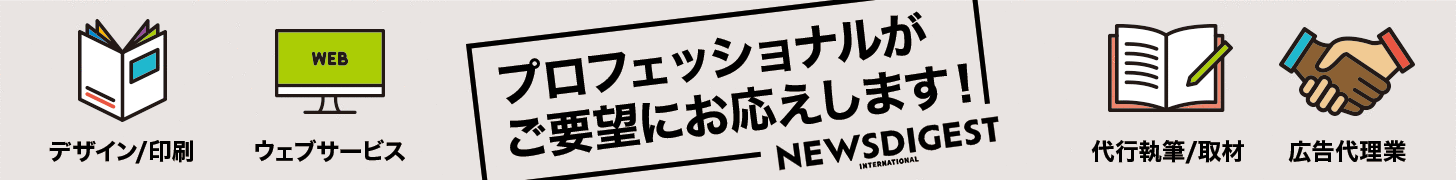

 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?