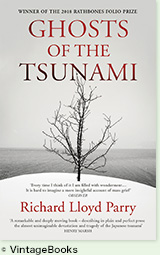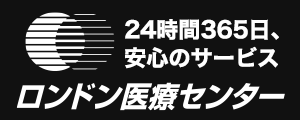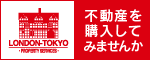東日本大震災から10年
英国のジャーナリスト&アーティスト インタビュー
2人の英国人が見たあの日のこと
2011年3月11日14時46分、マグニチュード9.0の激しい揺れが東北地方を中心に東日本を襲ったあの日。地震と津波で1万8000人以上の犠牲者が出たあの東日本大震災から、今月11日で10年を迎える。まずは、改めて亡くなられた方々のご冥福を祈りたい。今回は、未曾有の事態を「本と活字」で世に伝えた「タイムズ」紙のアジア・エディター、リチャード・ロイド・パリー氏と、「彫刻作品」として新しい解釈を広めた英国を代表するヴィジュアル・アーティスト、ルーク・ジェラム氏にインタビューした。表現を生業とする2人の英国人にとって、東日本大震災はどのように映ったのだろうか。
「タイムズ」紙 アジア・エディター
リチャード・ロイド・パリー氏 Richard Lloyd Parry
ヴィジュアル・アーティスト
ルーク・ジェラム氏 Luke Jerram
インタビュー No.1
ジャーナリストとして、感情にのまれず犠牲者に共感し続けること
「タイムズ」紙 アジア・エディター / リチャード・ロイド・パリー氏
1人目は「タイムズ」紙のアジア・エディターのリチャード・ロイド・パリー氏。1995年より東京在住のロイド・パリー氏は、2011年3月11日、東京のオフィスにいた。長期間に及ぶ取材を経て、被災者の心の動きに迫った「Ghosts of the Tsunami Death and Life in Japan」(2017年)は、翌年に日本語翻訳版も発行され、「英国人記者が日本人の特性を正確に捉えつつも、俯瞰的な視点で震災を見つめたルポ」として、好評を博した。本インタビューを通し、記者らしい的確な言葉選びに垣間見える、同氏の日本に対する温かなまなざしを感じてみてほしい。
 Richard Lloyd Parry
Richard Lloyd Parry
1969年生まれ、オックスフォード大卒。「タイムズ」紙のアジア・エディター。1995年より東京在住。「インディペンデント」紙の特派員として来日、2002年からは「タイムズ」紙のエディターとして、日本だけでなく北朝鮮、アフガニスタン、イラクなど29カ国をカバーし、ニュースを伝えてきた。書籍は本作のほか、1990年代後半に訪問したインドネシアのスハルト政権下における闇を描いた「In The Time Of Madness」(2006年)、2000年、神奈川県で英国人女性がバラバラ遺体で発見されたルーシー・ブラックマンさん事件を記した「People Who Eat Darkness Love, Grief and a Journey into Japan’s Shadows」(2012年、
翻訳版は早川書房「黒い迷宮─ルーシー・ブラックマン事件 15年目の真実」)がある。
Twitter: @dicklp
書籍
「Ghosts of the Tsunami Death and Life in Japan」
「津波の霊たち─ 3・11 死と生の物語」
東日本大震災発生直後から現地に通い、6年の歳月をかけ、震災が人々にもたらした心の傷とその後を丹念に追ったルポ。津波に巻き込まれてしまった宮城県石巻市立大川小学校の74人の児童と10人の教職員の遺族たち、被災者が紡ぎ出す言葉に耳を傾ける仏教僧など、さまざまな立場の人物を通じ、同地に残る震災の余波を取材した。本作は2018年、優れた英文学作品に贈られるラスボーンズ・フォリオ賞を受賞、2019年にはジャーナリズムの発展につながる活動をした者に贈られる日本記者クラブ賞特別賞を受賞した。
あの日、何が起こったか
2011年3月11日は、どこで何をされていましたか。
地震が発生したとき、私は銀座にある10階のオフィスにいました。当時すでに16年の在住歴があり、小規模の地震には慣れていましたが、あの日の揺れは私が今まで経験したなかで最も強いものでした。私は生まれて初めて自分の机の下に潜り込みました。窓ガラスがブーンと低くと唸り、ブラインドのビニール部分の端同士がぶつかり合いシャーッと震えたあの音を今でもはっきりと覚えています。後になって振動が6分間続いたことを知りましたが、揺れている間、時間の経過を測るのは困難でした。恐ろしかったのは、揺れそのものではなく、いつ終わるか分からないまま揺れが強くなり続けたことでした。
幸いにも、私のオフィスで被害はありませんでした。ようやく電話で連絡が取れたとき、パートナーも幼い娘も無事でした。2日後、別の地震(この地震の余震)がありましたが、大きな事故はなくおさまりました。私はこの地震もある程度の被害の原因になると考えましたが、「災害」と呼ぶレベルではありませんでした。巨大な波が野原、家、車を襲う空撮の映像を見て、先の地震がどんな大惨事であるかを理解し始めたのは後になってからのことでした。
震災後、すぐに取材のため現地に向かわれたようですが、そのときに目にした光景や感じたことを教えてください。
翌朝、同僚のジャーナリストの小さなグループと一緒に現地へ向かいました。高速道路は閉鎖されており、東京から仙台まで24時間かかりました。最初に訪れたのは、波で浸水した仙台空港で、木の枝に押し上げられている軽飛行機があったのを覚えています。
約2週間三陸海岸沿いをあちこち移動し、波にさらわれた町を訪ね回りました。南三陸町はおそらく最悪の被害状況で、町のほぼ全域が壊滅状態でした。最も変わり果ててしまったのは気仙沼でしたね。津波で港に停泊していた大型外航船が岸に激突し、燃料が漏れて発火。これによりある地域ではまず浸水、次に火災に見舞われました。巨大な船の一つは町のなかに漂着し、そのまま道路に残っていました。
最も奇妙なことは、この種の破壊は私にとって初めてみる光景ではなかったという点です。2004年のスマトラ島沖地震の津波について報告したインドネシアのアチェ州で、同じような惨状を見ているのです。あのとき、私はこう思いました。「人間が100年に一度見るか見ないかくらいの異常な経験だ。ひどすぎる。ぞっとする意味での『名誉』とも言える。私はこのようなものを目にすることは今後二度とない」と。
しかし、7年も経たないうちに、今や故郷となった日本で再びそれを見ることになってしまいました。
この本を書いたり、新聞に津波の記事をレポートする過程で、私は悲嘆に暮れ、耐え難い苦悩に直面しました。時に悲しさで満たされてしまうこともありました。これは、戦争や災害を報道するジャーナリストや、そのような状況下で働く援助労働者や医療の専門家が直面する課題です。どうすれば痛みに圧倒されることなく、大惨事の犠牲者に共感し続けることができるのでしょうか。
まだ自分のキャリアが浅いころは、それが難しく感じられました。しかし、しばらくすると、分離のコツを会得できるようになります。重要なことは仕事に集中すること。もし痛みに押しつぶされてしまうならば、良いインタビュアーやレポーターになることはできません。状況を分析し説明することは、ある程度状況から身を引くことを余儀なくさせます。結局のところ、ジャーナリストとしてどんなに辛く感じても、友人や家族、家を失った人々の悲しさに匹敵するものではありませんから。
だから私は職務を果たすことができました。代わりにその年はたくさんの悪夢を見ましたけれど。今でも海が近い場所でぐっすり快適に眠ることはできません。
書籍「Ghosts of the Tsunami Death and Life in Japan」について
「タイムズ」紙でのお仕事を抱えながら、書籍の執筆に取り組まれたその原動力は何だったのでしょうか。また、震災にまつわる痛ましい出来事が数多くあったなかで、大川小学校を選んだ経緯を教えてください。
新聞を通したジャーナリズムで災害の規模と恐怖を捉えるのは非常に難しいことだと早い段階で認識しました。私は以前に本を出版していたので、今回のことが書籍レベルの長さに値する物語であると理解していましたが、それを伝える方法を見つけるのには苦労しましたね。この災害全体を網羅する本を作ることはできない。ならば入口を狭く、一個人についての人間的なストーリーを追うことで、より大きな部分、自然の脅威やコミュニティー、そして当局の対応が見えてくるのでは、と。鍵のかかったドアの開け方を見つけるようなもので、私にとって大川小学校と幽霊の話がそれでした。
全ての死は痛ましいことで、悲劇をランク付けするのは間違っています。しかし、大川小学校と石巻市釜谷地区で失われた命よりも悲惨な事件を特定するのは困難です。
本書を書くにあたり、現地の人に多くのインタビューをされたと思います。そのときはどのような気持ちで行われたのでしょうか。その中で記憶に残っている印象的な話、また本に書ききれなかったエピソードがありましたら教えてください。
東北でたくさんの方々に会いました。その人々は私と話したいと思った人、話したくない人の2つのカテゴリーに分類されました。
執筆した本に登場した人物は、明白な理由で、私と話した方々です。私は数年にわたり、この本の中心となる何人かと会話を重ねました。会話を続けるなか、私はその方々に親しみを覚えました。話し手の気持ちや経験を書くことに最善を尽くし、それ自体はある程度の成功を収めたと信じています。しかし、私はほかの全ての人々、沈黙を守る被災者の存在を心に留めていなければなりません。その人たちにも一人ひとり異なる物語や感情があります。東北地方には震災について話さない、あるいは話したことが一度もない人が多いように感じます。私には謎ですが、きっと目には見えない悲劇があったかもしれず、それは10年後も続いているのでしょう。
私がそう思う一人に、大川小学校の被災校舎に行くたびに見掛けていた男性が挙げられます。その男性の7歳の息子は学校で亡くなりましたが、遺体はまだ回収されていません。男性は雨の日も晴れの日も、息子を探しに毎日出掛けました。時に泥を掘り、時にボートに乗って海にも出ました。ジャーナリストと一切話すことはありませんでした。
ラスボーンズ・フォリオ賞を受賞し、多くの人が本を手にしました。執筆後、何か心境の変化はありましたか。
質問を正しく理解しているかどうか分かりませんが、本の書き方について考えを変えたかどうかを尋ねられた場合、答えはノーです。書き直したいことは何もありません。
 地震発生時刻に大川小学校の前で黙とうする人たち=2020年3月11日、宮城県石巻市「時事(JIJI)」
地震発生時刻に大川小学校の前で黙とうする人たち=2020年3月11日、宮城県石巻市「時事(JIJI)」
東日本大震災から10年。これからのこと
岩手県陸前高田市立気仙小学校では迅速な避難により全児童の命が守られました。一方、大川小学校は天災に加え、人災によって拡大した被害がありました。命の明暗を分けたのは防災意識にあったと言われていますが、そうした意識は時間の経過とともに薄れてしまうのが現状です。数年にわたり足繁く被災地へ通われたロイド・パリーさんだからこそ言える、これだけは覚えていて欲しいと思うことは何でしょうか。
私は日本人に講義をするためにこの本を書いたのではありません。私の役割は、読者が各々の結論に到達することを期待して、可能な限り完全かつ示唆に富んだ物語を伝えることです。
日本は私が知るほかのどの国よりも、自然災害に対する備えが整っています。遅れているのは政治です。私の経験から言うと、日本人は政治を自分たちからかけ離れているものと見なしているように感じます。まるで政治が「別の自然災害」であり、その国民は無力な犠牲者であるかのようです。しかし、民主主義下では、自分でリーダーを選び、そしてある程度のふさわしいリーダーを獲得するものです。
新型コロナの影響で、国内移動が制限されている昨今ですが、状況が落ち着いたら東北地方へ足を運ぶ機会があることを祈っております。
英国とは異なり、国内旅行に法的な制限は現在ありません。来週は4年以上ぶりに大川小学校に行ってみたいと思っています。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?